<特殊詐欺>40,50代の被害急増 電子マネーを悪用
- 詐欺・悪徳商法
- 2017年7月25日
振り込め詐欺や還付金詐欺などの特殊詐欺に、40、50代で被害者となるケースが増えている。2017年1~6月の上半期に、広島県内で40代が28人、50代は22人が被害に遭い、昨年1年間の被害数(40代17人、50代22人)を超えるペースだ。背景には、パソコンや携帯電話でだまし、電子マネーを悪用する手口の増加がある。電子マネー詐取は1~6月に59件約1918万円に上り、昨年1年間(47件計約1562万円)を既に超えた。県警の佐藤百実(ももみ)・減らそう犯罪情報官は「若い世代の被害も増えてきており、社会全体で防ぐ必要がある」と訴える。【松井勇人】
県警のまとめによると、65歳未満の被害は「有料サイトの利用料を払え」などの架空請求が中心。パソコンやスマートフォンを閲覧中に警告や表示が画面に現れて支払いを要求するものや、携帯電話のSMS(ショートメッセージサービス)で請求を送りつけ、電話を掛けさせるなどの手口が多い。さらに、アマゾンギフトカードなど手軽に入手できる電子マネーを購入させて認証番号を聞き出したり、コンビニエンスストアのマルチメディア端末へ誘導し収納代行を悪用したりして金をだまし取る手口が増えている。
県警は2020年までに県内の特殊詐欺被害総額を5億円以下に抑える数値目標を掲げる。銀行員や郵便局員が現金自動受払機(ATM)コーナーや窓口で声を掛けたり、不審電話を把握した際に署員が無人ATMを巡回したりして、ターゲットにされやすい高齢者を被害から守る「水際作戦」を強化。また、一部金融機関では過去1年間にATMの振り込み機能を使っていない70歳以上の利用者のATM振り込みを制限した。県警は、こうした取り組みで6月末までに176件約1億3000万円の被害を防止したとしている。
電子マネーやコンビニ端末での被害急増について、県警は「無人の場所、第三者を介さない方法が狙われている」と分析する。また「電子マネーやマルチメディア端末など、若い世代だからこそ使えるという盲点を突いている」として、今後、コンビニなどと協力し、電子マネー購入者に特殊詐欺への注意を呼びかける方針だ。
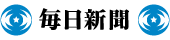


コメントする