タワマンなしでは成り立たない再開発…「下町」にタワマンが急増する意外な理由
- 政治・経済
- 2025年11月10日

再開発は、これまで新宿や池袋、東京駅周辺などの都心部を中心におこなわれていたが、今やその動きは都心部だけにとどまらない。かつては湾岸エリアの象徴だったタワマンも、最近では十条や金町などの下町でも続々と誕生している。なぜ今、「下町」でタワマンが急増しているのか。その背景には、都心部のタワマンとは異なる「再開発」の実態があった。
タワマンは下町でも建設が相次いでいる
日本で最初のタワーマンションは1976年に現在のさいたま市で完成した「与野ハウス」と言われている。都内では2000年以降にタワマンの建設が活発化した。勝どき・月島では2000年に都営大江戸線が開通して以降、タワマンの建設が相次ぎ、下町は高層ビル群に生まれ変わった。豊洲では東京ガスの工場や東京石川島造船所の跡地を活用し、2010年までに40階超のタワマンがいくつか建設された。
タワマンといえば、湾岸や港区などの都心が主だったが、下町でも建設が相次いでいる。葛飾区・金町駅では南口側に2棟が建っている。従前はアーケードの商店街や雑居ビルがあったエリアだ。2009年に竣工した「ヴィナシス金町タワーレジデンス」は地上41階建て。低層階にはマルエツや大戸屋などの店舗や葛飾区立中央図書館があり、上層階は住宅である。
2021年には駅前ロータリー前の区画に高さ86メートル・地上21階建て「プラウドタワー金町」が竣工した。ヴィナシスと同じく低層階には店舗や飲食店のほか、区の公益施設「カナマチぷらっと」がある。駅の北口では2030年をめどに地上40階建てのタワマンが完成する予定だ。
下町は3棟が並ぶタワマン街に変わろうとしている。同様の再開発は十条駅前で行われたほか、立石・小岩でも事業が進められている。
下町で典型的なタワマンができるワケ
ヴィナシスは「金町六丁目地区第一種市街地再開発事業」として建設された。市街地再開発事業には第1種と第2種があるが、いずれも高層化で生まれた新たな床を新しい居住者に売却して得る収入(=保留床処分金)をあてにしている。
プラウドタワーも第1種だ。第1種では従前の地権者が再開発ビルの床の一部(権利床)を得る。たとえば400戸中30戸は旧地権者のものとなり、残りの370戸をデベロッパーが分譲する。
むろん、市街地再開発事業では行政が絡むことになる。再開発に伴う容積率の割増や補助金の投入を決め、そもそもの許可を出すのは行政だ。タワマンは人口増加につながるほか、周辺の開発促進、都市のイメージアップなどにつながるため、行政は誘致に積極的である。
ただし、公金を投入するには大義名分が必要であるため、低層階の一部には図書館などのハコモノが設けられることが多い。また、駅前などの好立地を生かして低層階には店舗が入居する。民間単独の事業であれば、普通の低層マンションのように住戸や店舗だけの建物が建設されるはずだ。
つまり、低層階に公共・商業施設、高層階に住戸というタワマンの構造は、売りたいデベロッパーと公金を投じる行政の意向に沿って最適化された構造といえる。
富裕層?外国人?一体誰がタワマンを買っている?
都内の新築マンション価格は上昇し続けている。平均価格は2017年に7,000万円を超え、コロナ禍でも上昇が続き、1億円を突破した。港区など1等地にある2~3億円以上する物件が価格を引き上げているため、一概には言えないが、23区内の場合、駅チカであれば低層マンションでも1億を超える時代である。 2027年引き渡し予定で32階建ての「シティタワー綾瀬」は現在、2LDK・3LDKの9戸が9,900万円~1億3,900万円で販売されている。
近年のマンション価格高騰は供給側と需要側の両方の要因がある。供給側の要因は建築費や原材料費の高騰だ。円安や物価高、人件費の高騰で建築費が高騰しており、23区内のマンションでは建築費だけで坪単価250万円超のコストがかかる。販売価格では、坪単価400万円以上でなければデベロッパーの採算が取れないのが実情だ。
需要側に関しては旺盛な住宅需要が背景にある。特にタワマンの場合、8割を占める主な購入者は世帯年収1,500万円超の夫婦「パワーカップル」だ。ほかには経営者や資産家など。巷でいわれる外国人富裕層は少数派にすぎない。パワーカップルはステータス性に惹かれ、郊外からの通勤を避けたいという理由でタワマンを選ぶ人が多い。
かつて「ローンは年収の5倍まで」という安全基準があったが、7、8倍超のローンを組む人も増えた。金融機関も40、50年の長期ローンを提供している。パワーカップルはこういった長期ローンや、ペアローンを活用し、高価な都内のタワマンを購入している。
工事費が高騰も…再開発を支える「とある存在」
前述の通り、第1種市街地再開発事業は「保留床処分金」をあてにしている。タワマンの購入者はパワーカップルであるため、彼らによる住宅需要が再開発を支えているのが実態だ。だが高騰する工事費が保留床処分金を上回り、頓挫した事例もある。
中野サンプラザの建て替え計画では2021年に野村不動産を代表とする企業グループが施行予定者に決定された。だが2024年10月、工事費の高騰を理由に野村は施行認可申請を取り下げた。
当初の案は低層階にホールや店舗、中層階には住戸があり、上層階に事務所がある構造だった。24年1月時点で工事費は当初の試算(1,210億円)から1,845億円に増加。この時点では2,161億円の保留床処分金で賄えるという判断だったが、工事費がさらに約900億円増える見込みとなり、賄えなくなるため野村は申請を取り下げたとみられる。
その後、野村は保留床処分金を増やすため住戸部分の比率を増やしたツインタワー案を中野区に提出。区は住戸メインの再開発を不服として計画を白紙化した。オフィス・商業部分が多い高層ビルは中野区では採算が取れず、結局はタワマンに頼るしかないことを表した事例といえる。
工事費の高騰は再開発に待ったをかける。津田沼駅前の複合商業施設「モリシア津田沼」も50階程度のタワマンを含む複合施設として再開発する計画だったが、工事費の高騰などを理由に中断。部分的な再開を検討しているという。今後、首都圏のマンション需要が急減するとは考えにくいが、仮に需要が落ち込んだ場合、タワマンに頼る再開発は供給・需要の両側の理由で成り立たなくなるだろう。
ビジネス+ITより転用


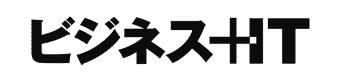
コメントする