「被災鳥居」残った 保存遺構候補外 「後世に」と住民ら動く 熊本地震
- 政治・経済
- 2017年10月27日
 地域の歴史と熊本地震の被害の大きさを後世に伝えようと、南阿蘇村の長野阿蘇神社の氏子や住民は、被災した鳥居を震災遺構として保存する。28日の秋季大祭に合わせて建立した新たな鳥居の隣に、壊れた鳥居の柱部分を並ぶように立て直した。被災した鳥居は県や村が保存する震災遺構の候補にならなかったものの、専門家は「地震を知らない将来の世代に被害を伝えるため、こうした地域の動きは大切だ」と評価している。
地域の歴史と熊本地震の被害の大きさを後世に伝えようと、南阿蘇村の長野阿蘇神社の氏子や住民は、被災した鳥居を震災遺構として保存する。28日の秋季大祭に合わせて建立した新たな鳥居の隣に、壊れた鳥居の柱部分を並ぶように立て直した。被災した鳥居は県や村が保存する震災遺構の候補にならなかったものの、専門家は「地震を知らない将来の世代に被害を伝えるため、こうした地域の動きは大切だ」と評価している。
神社は国選択無形民俗文化財「長野岩戸神楽」で知られ、鳥居は1917年に天草地方の石工が造ったとされる。昨年4月、地震により鳥居は壊れて1本足で立っている状態になった。倒壊の恐れがあったため重機で横倒しにし、1年半にわたって神社の前に置かれたままになっていた。
氏子総代の北里剛さん(76)らは「地震のシンボルとして鳥居の一部だけでも残したい」と主張してきた。ただ、保存にかかる費用と安全への配慮から撤去を求める声もあった。
9月19日に撤去作業の安全祈願祭が営まれたが、その後の住民の会合で、保存を望む声を尊重し、鳥居の柱部分のみを残すことを決めた。新たな鳥居の修復費は、県の復興基金から4分の3が補助される。施工業者の好意で、横倒しの鳥居も併せて立て直してもらえることになったという。長野修一区長(60)は「並べて置くことで地震の被害を想像してもらいやすい。説明の看板も設けたい」と話す。
県は断層が目に見えてずれた箇所など5町村の49件を震災遺構として保存するよう検討しており、村も崩落した阿蘇大橋の橋げたなど12件を候補としている。一方で被災しながらも遺構の候補外となり、保存が難しい建造物も各地にある。震災遺構に詳しい熊本大の鳥井真之特任准教授(地質学)は「住民目線の価値観を大切にすることは非常に素晴らしく、できる範囲で記憶を継承してほしい」と話す。
◇ ◇
秋季大祭は28日に神社であり、午後6時から長野岩戸神楽が奉納される。見学は無料。
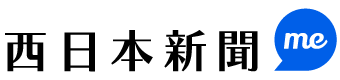
一言コメント
住民の意見が通りますように・・・。


コメントする